
崎山貝塚に人々が暮らしていたのは、主に縄文時代の前期(6,000年前)から後期(3,000年前)
で、およそ3,000年間にもわたりました。時期毎に、遺構(ムラの形)の配置が違うことから、5段階の移り変わりが考えられます。まとめると下の年表のようになります。第3段階と呼ばれる頃にモンちゃんはくらしていたんだね。
| 古代の日本史上の崎山貝塚 |
 |
縄文時代は、今からおよそ1万年以上前に始まり、2,300年前まで続きました。 崎山貝塚に人々が暮らしていたのは、主に縄文時代の前期(6,000年前)から後期(3,000年前) で、およそ3,000年間にもわたりました。時期毎に、遺構(ムラの形)の配置が違うことから、5段階の移り変わりが考えられます。まとめると下の年表のようになります。第3段階と呼ばれる頃にモンちゃんはくらしていたんだね。 |
| 宮古市教育委員会による |
| 時代の様子 | 崎山貝塚 | 海水面 | 気候 | 植物相 | 動物相 | |||
| ムラの様子 | 貝塚の様子 | |||||||
| 旧石器時代 | ・寒い時代(氷河期)が続く。 ・日本に人々が住みつく。 |
|||||||
| 縄文時代 | 草創期 | 1万2000年前 ・氷河期が終わり縄文時代が始まる。 ・土器と弓矢が発明される。 |
-20〜40m | 次第に多雪化。 北日本は寒冷気候。 |
ブナ林の拡大 | ・現生種の時代 | ||
| 早期 | 9000年前 ・各地に貝塚が造られ始める。 |
・このころから人が住み始める。 | (10m/1,000年の上昇) | 海洋性気候の確立。 今の環境に近くなる。 |
ブナ林がほぼ現在に近い分布域に達する。 ブナ属の増加(イヌブナ属) エノキ属・ムクノキ属・モミ属・ツガ属 ○西日本の低地からブナ林が消滅。東日本以北がブナ属分布の中心地に。 |
・ブラキストン線の確立。 本州と北海道で亜種の分化。 |
||
| 前期 | 6000年前 ・気候が温暖化し、海面上昇のピークを迎える。 ・十和田火山が噴火し、火山灰が降る。 ・各地に貝塚が多く造られる。 (陸前高田市牧田貝塚) (宮古市千鶏遺跡) |
★第1段階 発掘された遺構で縄文前期のものは、土坑(どこう)跡(土を掘った穴の跡)が2基だけで、ムラの様子がよく分かっていません。中期以降の人々がムラを造るときに、古いムラを壊したと考えられます。貝塚や土器の捨て場の様子から、前期にも大規模なムラが造られていたと考えられています。 |
・魚や獣の骨を中心とした貝塚が造られる。 ・斜面部に大規模な土器捨て場が造られる。 ・火山灰が降下する(5,500年前の十和田噴火) |
縄文海進+2〜3m (説により+5〜6m) |
温暖化と冬期の積雪量減少。 | ○西日本のブナ林孤立分布。 ○東日本のブナ林後退。 |
○三陸沿岸の貝塚 ・ハイガイの北上。 |
|
| 中期 | 5000年前 ・ムラの数が全国的に最も多くなり、規模も大きくなる。 (紫波西田遺跡) (一戸町御所野遺跡) (宮古市高根遺跡) ・前期に続き貝塚が多く造られる。 (大船渡市蛸ノ浦貝塚) (陸前高田市中沢浜貝塚) |
★第2段階 中央部にお墓や土坑跡、西部に竪穴式住居跡が見つかっていますムラの中心部にお墓が造られ始める。 |
・岩礁性二枚貝を中心とした貝塚が造られる。 |
|||||
| ★第3段階 中期以降は、ムラの中央にお墓や広場を持つ規則正しい配置の大規模なムラが造られます。ムラの中心部が島状に高くなり、周辺がドーナツ状に低くなっています。 環状遺構帯と呼ばれています。大規模な土木工事によってできたものと考えられ、形が他の遺構には見られない珍しいものです。 大規模な土木工事によりムラを造る。 (他に例を見ない形となる) 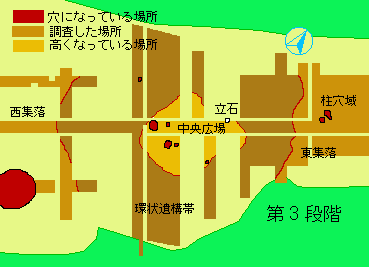 |
・斜面部に大規模な土器捨て場が造られる。 | |||||||
| ★第4段階 環状遺構帯が次第に埋没し始めると、中央広場から環状遺構帯にかけて、無数の土坑が堀りこまれるようになります。この中には、お墓もありますが、ほとんどは木の実などの食料貯蔵用のものと考えられます。土坑跡の周辺からは、殻がむかれたドングリがまとまって見つかっています。ドングリなどの木の実を食料とするための共同作業やお祭りなどをする場所だったと考えられます。外側には、東西両側に居住区域がありますが、次第に中央部に寄ってきます。 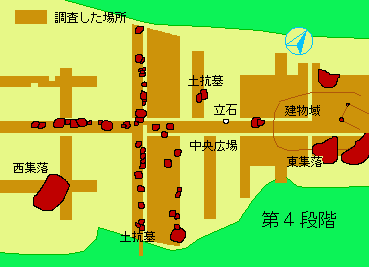 |
||||||||
| 後期 | 4000年前 ・ムラの数が次第に少なくなる。 ・ストーン・サークルが造られる。 (秋田県大湯環状列石) (大迫町立石遺跡) (花泉町貝鳥貝塚) (陸前高田市門前貝塚) (宮古市わたのは遺跡) |
★第5段階 ムラは規則正しい形ですが、次第に規模が小さくなっていきます。中心部分に遺構が全くない円形の中央広場があり、外側に二重の輪状に遺構が配置されています。内側の輪は、配石遺構という石を並べたお墓や立石で構成されています。外側の輪は、配石遺構、お墓(土坑墓)、マグロの骨をまとめて埋めた穴、立ったまま出土した石棒(東側に位置)、土器片を敷きこの上で火をたいた穴、竪穴式住居跡で構成されています。ムラの形はストーン・サークルにとてもよく似ています。第3段階から第5段階へのムラの移り変わりを調べることにより、ストーン・サークルが成立する様子が詳しく分かる可能性が大きいと言えます。 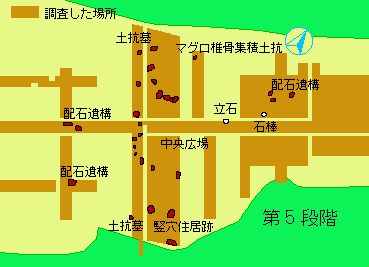 |
・斜面部に小規模な土器捨て場が造られる。 | |||||
| 晩期 | 3000年前 ・ムラの数がとても少なくなる。 ・薄手で精巧な土器が造られる。 (大船渡市大洞貝塚) (宮古市近内遺跡) |
・少量の遺物が出土。 | やや冷涼化。湿潤化。 冬期の積雪量増加。 |
・ブナ属の拡大(スギ属と競合) | ||||
| 弥生時代 | 2300年前 ・稲作が始まる。 (宮古市上村貝塚) |
・少量の遺物が出土。 | 現在と同じ | ・現在の自然植生分布と同じ。 | ||||