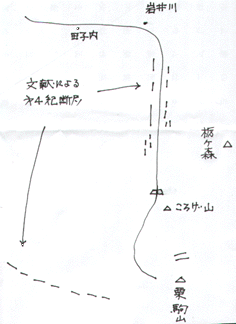成瀬ダム予定地点の地質学的ようす
成瀬の水とダムを考える会事務局
熊沢 文男
1 凝灰岩
現地に顔を出しているのは凝灰岩です。海底の火山活動で噴出した灰などがたまって出来たものですから、壊れやすい岩です。院内石もその一種です。
大昔、秋田県全体が海の底でした(羽越地向斜)。
2 まっすぐな成瀬川
現地仁郷から岩井川まで、川は南から北へまっすぐに下っています。なぜでしょう。昔、大地にまっすぐなヒビが出来て(断層)、そのヒビに沿って川が流れているのです。
東北地方の背骨には奥羽山脈があります。山脈のある場所の東と西から、強い力で、押され続けて、真中に山脈が出来ました。真中が盛り上がっていくとき、ヒビ(断層)が縦に出来ました。
東北地方の地図を見てください。北上川は一番長いヒビです。山形の最上川も長いヒビです。雄物川の主流も、横掘の方から秋田に向かう長いヒビです。どれも南北に流れています。
大地が動いてヒビが出来ます。これを構造線(こうぞうせん)とも呼んで
います。増田町の狙半内川も、短い構造線です。これも南北です。
3 二種類の構造線
現地の構造線を、建設省の資料で見るとき、南北と東西、2種類の構造線
(ヒビ)に気付きませんか。(略図参照)
南北の構造線は、前に述べた奥羽山脈と関係あります。奥羽山脈は今も少
しずつ押し上げられ、高くなっているはずです。
成瀬川の南北の構造線は、ダム予定地点の手前で終わっています。これは
ほんとうは栗駒山まで延びていると思われます。
栗駒山は若い山です。活火山で時々噴火します。その時、噴き出した岩が構造線の上にかむさって、見えなくなっていないでしょうか。
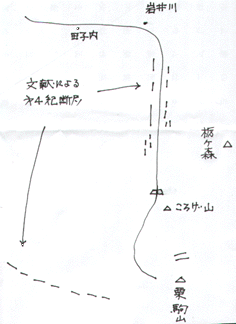 |
 ヨーロッパアルプスの構造線
|
(詳しい地図を見たい場合は略図上でクリックしてください)
4 東西にのびる構造線
それとは別に、東西にのびる構造線があります。なぜ東西に出来たのでしょう。この地域は、南側と北側からも大地に大きな力がかかっているようです。
栗駒の西には秣岳、神室岳など、西へ向かっていくつもの火山が延びています。鳥海山も見えます。
東へ延びた先は牝鹿半島・松島方向へとつづきます。それぞれに構造線が南北にのびています。
栗駒山が高くなるときのヒビ割れは、成瀬川のヒビ割れより新しいのではないでしょうか。
5 大地が動く心配はないか?
大地が動いたからヒビ割れが生じました。今も動いていないでしょうか。
それを調べるには、横向きにキリで孔を明けて調べないとわかりません。
大地の表面を見ただけでは、落ちてきたりして溜ったもので、見えないからです。
横(水平)向きに孔をあけて調べる(ボーリング調査)ことが必要で、縦に突き刺しただけではわかりません。建設省がそれをやっているかどうか。
ダムが壊れないか、地震は大丈夫か。
横向きに、いろいろな方向に調査が必要です。
6 危ない「天然資源」
前の湯沢工事事務所安田所長は、現地は正に他にない天然資源といいました。あんなふうにポッカリと広い平地がある。成瀬川ではあそこだけです。ダムの最適地というわけです。
でも、なぜあの広場があるのか。2種類の構造線がまじわったから出来たのです。逆にとても怖い場所なのです。ほんとうに近く動くかどうかは別として、確率的にはよそより危ない「天然資源」なのです。
7 地すべり地帯
この問題については、わたしたちは不勉強です。ダム予定地の下流に有名な地滑り地帯がたくさんあり、建設省はそこを避けたと言っています。
おそらく、泥岩層の堆積の仕方に問題がありそうです。もしかすると、大
地が動くための「地すべり」かもしれません。地すべり地帯はどれも構造線に沿って並んでいますから。建設省は動いていないと言っていますが。
上の写真に見える構造線は、スイスからイタリアへ越えるアルプスで見た構造線の写真です。わたしが撮りました。ダム予定地点でも、建設省は、空
から、こうした写真を何枚も撮っています。
|